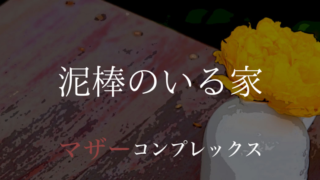――毎日をちゃんと生きる事。
それが、羽鳥恵子にとっての幸福だった。朝六時に起きて、お弁当を作る事。朝食を家族で食べる事。昼はスーパーのパートに出て、仕事をする事。従業員と談笑をする事。賞味期限が切れそうなお惣菜を貰って晩ご飯にする事。二十三時に布団に入る事。
そういった普通の事を毎日続けるのが、一番大切。そう思うようになったのは、パート先での人間観察がきっかけだった。生活の一部が覗けるスーパーでは、意外と普通ではない人が多く見られる。
恵子は何度か万引きの現場を目撃した事がある。万引きするのは何故か女性に多く、一見、普通の人ばかりだ。
中には、万引きを繰り返し行ってしまうという人もいた。彼女は、スタッフルームに連れられた後、娘がいるから警察に通報しないでくれと言った。自分と同年代くらいに見える人間が罪を犯してしまうのを見るのは、さすがに恵子も気が滅入った。
スーパーでは、あらかじめ万引きによる損害が出るように計算されている。万引きする人たちの多くは、本当にお金に困っている訳ではないらしい。お小遣いの少ない中高生以上に、中高年の万引きは闇が深い。
最近はよく、万引きをやめられない人の特集がテレビで放送されるようになった。流行なのだろうか、ここ数ヶ月で三回程見かけている。
「クレプトマニアっていうんですって」
「万引きする人のことぉ?」
高校生の娘萌絵は、最近語尾を少し伸ばして喋るようになった。夕食の焼きそばに青のりをふりかけながらテレビと恵子の顔を交互に見ている。
「そう、万引きを何度も繰り返してしまう人の事。うちのスーパーにもね、いたのよ。そういう人。一回じゃなくて、何回も繰り返すから、仕方なくこちらも警察に言うしかないの」
テレビ画面には、まさに自分が職場で何度か目にしている光景が映し出されていた。
「病気ってことぉ?」
「だと思う。そんなのいらないでしょうっていうようなものばかり盗ったりするのよ。必要のないものを何回も万引きしようって言う気持ちに、普通はならないでしょう」
「ふぅん」
恵子は注意喚起のようなつもりで話をしたが、萌絵には全く響いていない。自分とは別の世界の事だと思うと、人は話を聞かないものだ。特に高校生の頃なんて、それが顕著であると思う。
「七年間やめられないっていう人もいたよ。娘さんがいるって言ってたなあ」
「なんでそんな事がわかったの? 娘がいるとか」
萌絵が真面目な顔をして、恵子の目を見つめた。語尾を伸ばしていない時は、真剣な質問がある時だった。
「店長と話しているの聞いちゃったの。娘がいるから警察はやめてほしいって話をしてるところ。でも、もう何度も繰り返しちゃってると、子供がいるいないは関係ないのよね」
「その人、この辺に住んでるの?」
「スーパーが近いって事は、そうだろうね。お母さんがスーパーで働き始めた頃の話だから、もう引っ越しちゃったかもしれないけど」
「娘、かわいそう」
萌絵は、八重歯を少し見せながら下唇を噛んだ。
「みんな最初はきっと、普通の人なの、だけどどこかで何かを踏み外してしまう。それで普通じゃなくなっちゃうんだよね。だから毎日をね、ちゃんと、生きるのよ」
恵子は毎日をちゃんと生きてほしいという事を、スーパーで働き始めてから何度も萌絵に話していた。
「万引きなんかしないよぉ」
「万引きに限らず。なんでもね。ちゃんと生きていくって事が大切なの」
「お母さんの口癖だねぇ」
「その人、万引きが原因で離婚しちゃったらしいのよ。些細なきっかけで人生って変わってしまうんだから」
「だから、コツコツ毎日を、ちゃんと。ね」
萌絵はからかうように、恵子の口癖をなぞった。
「そう。みんなね、そんなに大きな事に発展するとは最初は思わないの」
「ねえ、その人、離婚してどうなったの?」
恵子の話を遮って、萌絵が質問を返した。
恵子は六年前に逮捕された女性の事を思い出せる限り話した。穏やかな性格の萌絵はぼんやりしている事が多く、母親の目から見て心配になる事も多かった。高校に入ってすぐのうちは楽しそうにしていたが、ここのところあまり元気がなく、話しかけても会話が続かない事が多くなっていた。それだけに、恵子の話に興味を持ってくれた事が嬉しかった。
薄手の長袖一枚で「うん、うん」と、頷く萌絵を見て、去年羽織っていたカーディガンを出しておこうと恵子は思った。今年は秋が長いから、衣替えのタイミングが難しい。
その年の暮れ、萌絵が自分の手首を深く切った。恵子が玄関に門松を飾っている時の事だった。それまでにも何度か萌絵の部屋から泣いているような声が聞こえていたので、いつも以上に気にかけていたつもりだった。しかしその行動も空しく、萌絵は突然発狂したように叫んで腕に大きな傷をつけたのだ。二階の部屋から、玄関まで聞こえるほどの大声だった。
恵子は泣きながら萌絵を病院に連れて行った。九針縫う大怪我だったが、終始渋い顔をしていた恵子に対して、萌絵はケロッとした顔をしていた。気持ちがコロコロ変わって情緒不安定な様子なのも、この頃の萌絵の特徴だった。
「リストカットと言って、中高生の間で流行っているみたいなんですよ」
縫合した医師が、淡々と話した。だから気にしなくてもいい、と話が続いていきそうだった。恵子はショックのあまり眩暈がした。
どうしてこんな事をしたのかと萌絵に尋ねても、「お母さんには関係ない」と言うばかりで話をしてはくれなかった。
数日後、長男の広軌が、とあるサイトで萌絵が日記を書いていると恵子に教えてくれた。サイトが出来た当初に、萌絵に教えて貰ったものらしかった。広軌は、三年前に就職で家を出てからも、恵子たちを度々気にかけてくれている。
恵子が携帯電話からアクセスしたサイトは、真っ黒の背景にシルバーの文字で、ギリシャ神話の登場人物が装飾されている。もう半年近く、ここで萌絵は毎日日記を更新しているようだった。そこには、付き合っている男の子へのラブレターのようなものが日々綴られている。あまり見てはいけない気がしたけれど、恵子は自分の娘に何があったのか知りたかった。
ちゃんとすることがだいじ
ちゃんとすることがだいじ
リストカットをした日の日記には、恵子の口癖が平仮名で書かれていた。それは萌絵のSOSである事に間違いなかった。恵子は携帯電話の画面の上に、涙を零した。
萌絵は自分の気持ちや状況を多く話すようなタイプではなかったが、穏やかな感情の中に時折激しさが見える子だった。リストカットをした時は、どこかで「やはり」という気持ちが恵子の中にあったような気がする。
いずれにせよ萌絵は、何かしら多くの事を感じて苦しい思いをしているに違いない。気にかけているつもりだったのに、足りていなかったのだ。言葉が足りなかったのか、気持ちが足りなかったのか、恵子は自身の行動と萌絵の行動を照らし合わせて、何が最善か考えた。あまり得意ではないインターネットを使って、掲示板で相談をしてみたりしたが、ピンとくるものは出てこなかった。
「今度の大会、萌絵と一緒に観に来たら? 子供たちが頑張ってる姿、結構泣けるよ」
広軌は、あれから電話をかけてくる頻度が少し多くなった。仕事をして一人暮らしをしながら、色々と考えてくれているのだと思うと、恵子に温かい気持ちが広がる。
「萌絵ちゃん、来てくれるかしら」
「母さんが言いにくいんだったら、俺が声かけとくけど」
「ありがとう。今部屋にいるみたいだから、自分で誘ってみるわ」
「うん、たまには親子で出掛けるのも、いいんじゃない」
幼稚園の頃から空手を習っていた広軌は、社会人になってからは近所の小学生に指導をする立場になっていた。萌絵が高校生になってからは、一緒に出掛けることはほとんどなくなったが、幼い頃はよく一緒に空手の大会を観に行っていた。
会場の近くには、家族で何度か訪れた事のある美味しいピザ屋がある。大会の後は萌絵と一緒にピザでも食べながら、最近の学校での話なんかを聞けたらいいかもしれない。恵子はそんな事を考えながら、もう長く行っていないピザ屋の内装を思い返す。鮮やかなイタリアの国旗が、木造の建物にかかっていて妙におしゃれに見えた。まだあのお店はあるだろうか。後で調べてみよう。広軌の優しさが、解決の糸口になるかもしれない。
「お兄ちゃんの大会を観に行かない?」
恵子は萌絵の部屋をノックして声をかけた。
女の子らしかった萌絵の部屋からピンク色が少なくなっている。いつの間にか、好きな色も変わってしまったのだろうか。
高校受験辺りから、萌絵の部屋を覗かないように気を遣っていたつもりが、そのせいで変化に気付いてあげられなかった。これからはなるべく部屋にも立ち入るようにした方がいいのかもしれない、と恵子は思う。
「どうしたの急に」
「子供たちの頑張ってる姿、泣けるよって。萌絵ちゃん、最近悩んでるみたいだから、心配してくれたのかな」
「悩んでる訳じゃないよぉ」
語尾を伸ばして喋る萌絵の声を聞いて、恵子は少しホッとした。機嫌がいい時の萌絵だ。
「お母さん、いつも萌絵ちゃんの味方だからね。何か相談があったら言ってね」
「相談って」
萌絵が鼻で笑う。幼い頃と変わらない、可愛らしい笑顔だった。
「一応お母さん、萌絵ちゃんより何十年か長く生きているからね」
恵子は手を握って、顔の隣でグーのポーズを揺らす。精一杯、口角を上げて微笑んだ。
「いいよぉ、大会。観に行く」
断られるかと思ったが、案外とあっさり二人で出掛ける事が決まった。恵子は携帯電話を使って、以前家族で行った事のあるピザ屋がまだあるかどうか調べた。グルメサイトに載っている営業時間が以前と変わらない。恵子は安堵する。メニューの欄に、萌絵が好きだった三種類のチーズが載ったピザがある事も併せて確認した。
大会の日の朝、バタバタと用意をしている萌絵を見て恵子はホッと胸を撫で下ろす。心のどこかで、当日になって断られるのではないかという不安があった。恵子はパートの時よりも少し丁寧に化粧を施した。
電車とバスを四十分程乗り継いだ先にある会場は、空手以外にもかるたやダーツなど、色々な大会が行われる。
「お兄ちゃんはさぁ、順風満帆っていう言葉が似合うよねぇ」
会場に到着する頃、バスの中で萌絵が言った。萌絵は自身の人生を順風満帆ではないと思っているのだろうか。恵子は一瞬、返事に躊躇した。
「そうかしら」
萌絵の髪を軽く整えながら、恵子は出来るだけ優しく微笑んだ。
「そうでしょ。高校も大学も、就職まですーんなりって感じだったじゃん。社会人になってもきっと会社でもうまい事やっていて、趣味の空手を小学生に教える日々。これぞ、順風満帆って感じ!」
「ふふふ、そうね。素敵な事じゃない」
「きっと私が普段考え込んでいるような事は、お兄ちゃんにとって取るに足らないような事だったりするんだよ」
「何か考え込んでいるの?」
「例えば、の話だよぉ」
萌絵は話をしながら、バスの停止ボタンを強く押した。バスを降りると、ダウンコートをくぐり抜ける程の冷たい風が吹いている。萌絵は恵子に歩幅を合わせて、ゆっくりと歩いた。
「小学生ちっさー! 可愛いねぇ」
会場に到着した萌絵は、突き抜けるような高い声で恵子に話しかけた。
「ついこの間まで萌絵も小学生だったように思うけど、いつの間にか大きくなっちゃったわね」
「さすがに高校生だからねぇ」
心なしか萌絵はいつもより穏やかな表情に見える。高校生になって精神的にもかなり自立してくる頃ではあるが、親子のコミュニケーションを取る事が萌絵にとっての癒しに繋がればいいと、恵子は思った。
空手の大会は団体戦で、一チーム五名で構成されている。広軌のチームは県内でも優秀で、今回の大会でも優勝候補とされていた。
萌絵は試合中、「あ!」や、「頑張れー」と言った声を上げて、チームの応援をしている。
「しかしこれは毎回ついてくる親も大変だね。みんな観に来てるのかな?」
「お兄ちゃんの時は、お母さん毎回行ってたわよ」
「でもこのチーム、両親共に来てるとこ多くない?」
萌絵が広軌のチームを指しながら言った。
「本当ねぇ、教育熱心な親御さんが多いのかも」
「わーお兄ちゃん、両親が揃って見に来てくれるような事はなかったよねー。そこだけは順風満帆じゃあなかったかぁ」
恵子は言葉に詰まった。突然虫の居所が悪くなったように萌絵は髪をかき上げた。
「お父さんも、一度見に来てくれた事あったわよ」
少し間を置いて恵子は返事をしたが、萌絵が被せるようにきつい口調をかける。
「いやでも一度だけでしょ? そんな付け焼刃みたいな応援、意味ないでしょ」
「一度も来てくれないより、いいと思うけど……」
「大体お母さんとお父さんって夫婦じゃないじゃん。そんな二人が一緒に来られても、迷惑だったに違いないよ。なんでそこで認めてごめんなさいって言えないの」
萌絵は眉と眉の間にキュッとシワを寄せて、空手をしている子供たちの方を睨むように見ている。
「ごめんなさい……」
「謝ったって、何も変わらないけどね。私が惨めな思いをして生きてきた事に変わりはないんだから」
恵子は持っていた手袋を両手でギュッと握りしめた。
恵子が未婚の母である事を知ったのは、萌絵が小学生の時だった。父親が週に二回程しか家に帰ってこない事を不審に思った萌絵が、広軌に尋ねたのだった。
事実がどのように萌絵に降りかかったのか、恵子にはわからなかった。けれどその後、萌絵の生活や態度が特に変化する事はなかったので、恵子は自身と同じようにこの生活を幸せだと感じてくれていると思っていた。
「惨めだと思っていたの?」
恵子は、唇が震えそうになるのを必死で堪えた。
「当たり前でしょ。お父さんがほかにも家庭がある人なんて、普通いないよ」
「でも、萌絵ちゃんの事も、家族の事も、ちゃんと大事に思ってくれているのよ」
恵子の言葉に被せるように、萌絵は大きく地団駄を踏みながら叫んだ。
「大事に思っていたら、そんな事にならない! あんたも人のもんだった男を盗ったんでしょう! スーパーで万引きするバカとどこが違うんだ! 偉そうにちゃんと生きろなんて言ってんじゃねえよ!」
会場に響き渡る程の大声だった。萌絵は言葉を返せない恵子を睨みつけ、そのまま足早に会場を後にした。恵子の身体は石になったように重く、動かない。追いかける事なんて、とても出来なかった。
重たい身体を引きずって、やっとの思いで会場の外に出た時、朝よりも風は強くなっていた。冷たく、頬を突き刺すような寒さだった。
萌絵の父親と出会った日の事を思い出す。同じように寒くて、悲しい冬だった。二十年以上時が経って、あの日何が悲しかったかなんて恵子はすっかり忘れてしまった。とにかく何だか落ち込んでいて何となく入ったバーで、隣に座った男性と、ごく普通に男女の仲になった。結婚している事なんて知らなかったし、特に知ろうともしなかった気がする。「妻とは別れるから」なんて言葉を聞いた時は、漫画みたいだなと思ったりした。あの頃、ほかにやりたい事なんてなくて無我夢中で恋をしていた。どうしてもあの人を手に入れたくて広軌を産んだけれど、あの人はいつまでも“妻”と別れてくれる事なんてなかった。子供というのは、男性を変える要因にはならないのだなとぼんやり思った。
エゴだった。今は本当に、そう思える。けれど広軌が生まれて、心の底から幸せだと思ったのも事実だった。いつまでも満たされない気持ちを埋めてくれたのは、紛れもなく広軌と萌絵だ。
あの人が私と結婚してくれる事はなかったけれど、毎週うちに来てくれる事もそれはそれで事実なのだ。広軌が「妹が欲しい」と言った時だって、すんなりと受け入れてくれた。
大切にされている。それで十分じゃないか。
何が、何がいけなかったのだ。
「ねぇ、お母さん。前にお母さんが話してた七年間万引きしてた人って、加奈のお母さんなんだよ」
空手の大会から数日後、何度話しかけても返事をしなかった萌絵がようやく声をかけて来た。しかしその言葉に、恵子は心底驚かされた。キッチンで一人、夕飯の準備をしていたところだった。煮込んでいた肉じゃがが、グツグツと音を立て始める。
「娘がいるから警察に言わないでとか言ってたんだよね? その娘が加奈だったの。知ってた?」
萌絵は、驚く恵子の顔を覗き込み、八重歯を見せて微笑んでいる。
加奈という名前は、萌絵が高校に入学した当初よく聞いていた。久しぶりに交わす会話が、あまりにも非日常的である事に戸惑い、恵子は言葉に詰まってしまった。
「なんでそれがわかったの?」
三秒程の短い沈黙の後、ようやく言葉が出たが、被せるようにして萌絵が話を続ける。
「苗字が同じだから怪しいなって思ってて、加奈に直接聞いてみたの」
確かに「日渡」という苗字だという事は話したかもしれない。そんなに身近にいるとは思いもしなかったので、名前を言ってしまった事を恵子は後悔した。
「なんて聞いたの?」
恵子が戸惑っている事など何も気付いていないように、萌絵は嬉々として喋っている。
「加奈ってよくお母さんの話をするから、注意深くずっと聞いていたら、どうも最近の話は嘘なんじゃないかって思い始めてね。本当にお家にお母さんいるの?って聞いたよ」
「加奈ちゃん、可哀相……」
恵子は思わず、萌絵を否定するような言葉を口に出してしまったと後悔した。けれど、当事者である女性の娘に直接万引きの話を聞くなんて、普通の感覚ではない気がしたのだ。戸惑う恵子に構わず、萌絵は話を続けた。
「最初は誤魔化してたんだけど、何度も何度も聞いているうちに、なんでそんな風に思うのって加奈が聞いてきたの。その時の顔を見て確信した。これは絶対に黒だってね」
「加奈ちゃんが、万引きをしたわけじゃないでしょう」
「うん、だから、加奈のお母さんが黒だよ」
フォローをしたつもりだったが、すぐに萌絵に言葉を返されてしまった。
肉じゃがが大きな泡を吹いて、鍋の蓋を浮かせている。恵子は火を止めた後、大きく息を吸った。
「あんまり、人の家の事をとやかく言うもんじゃないわ。そんな事、友達に聞かれたりしたら、嫌でしょう」
「でも、お母さんが教えてくれたんだよ。加奈のお母さんは万引き犯だって。物を盗るような、ちゃんとしていない人なんだって」
思いもよらぬ萌絵の言葉に、恵子は息が詰まるような感覚に襲われた。外からの強い風で、窓がガタガタと音を立てる。
萌絵が、普通ではなくなっていく。
第五章『クレプトマニア』終。
ーーーーー
第一章【漆の汁椀とマヨネーズ】
第二章【ママの書置き】
第三章【泥棒のいる家】
第四章【ベビーブルー】
第五章【クレプトマニア】
第六章【二人のマコト】
第七章【私のアドニス】
最終章【マザーコンプレックス】